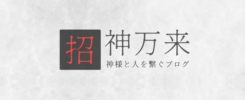楽太郎です。
今回は、「日月神示」解説になります。
私が別名義で運営している日月神示解説サイト、「HITSUKU」にて、以前「荒れの巻」のルビ振りと口語訳に関するページを投稿していましたが、当時の「当て字」の読みを今見直してみて、より解像度の高い解釈を見つけたので、内容をアップデートしました。
そして、今回の記事は「荒れの巻」解読から紐解いた「真の天照大御神、伊奘冉命説」を掘り下げていきたいと思います。
「荒れの巻・口語訳」
「荒れの巻」の仮名遣いについて
今回注目したのは、「字」の読み仮名です。
これまでは「ふじ」という読み方をしていて、だいたいその意味でも何となく繋がっている印象がありました。
「日月の巻・第六帖」には、こうあります。
「一度は何もかも天地に引き上げと申してあるが、次の世の種だけは字に埋めておかねばならんのだぞ」
これを読んだ時、「字」は「地(ち・じ)」と同じ使い方をされていることに気づきました。
日月神示は主に数字や記号などの羅列で降ろされるため、口語体に変換する際には、読み仮名に法則のようなものが存在します。
例えば「じ」と読める場合、数字の「二」に逆変換することができます。
これは「富士・不二(二二)」などに見られる用法ですが、「二」は「一」の「つぎ」だから「二(つぎ)」と読むことができます。
このように、神示の解読にはイマジネーションを働かせる必要があるのですが、この「つぎ」という言葉は「つき」という用法に転嫁することが可能です。
「字」を「つき」と読むようにしたところ、その部分を「荒れの巻」から一部拾ってくると、以下になります。
「字の極意の極みは読字ぞ、富士に花咲く時だぞ、開く結びの命、字開き、字開きて実るぞ」
これを私なりに読み仮名をつけて一文にすると、こうなります。
「月の極意の極みは世継ぎぞ、富士に花咲く時だぞ、開く結びの命、月開き、次開きて実るぞ」
「字=つき」が「継ぎ・月・次」と、まるで違う言葉に変換されています。
こういったバリエーションを読み解くのも神示をよく読み、神示に頻出する語彙を紐付けていくと、一応は納得できる文脈になってきます。
「月」の神であられる伊弉諾命が「地の岩戸」を開いて顕現すると、真の天照大御神こと伊奘冉命の座す「岩戸」をまた開くことで世に光が戻り「ミロクの世」となる、その文脈がここに再現されます。
こうして「字」を「つき・つぎ」と読むことで、神示にある「岩戸開き」の真髄が「伊弉諾命の世継ぎ=天照大御神襲名・天日月大神即位」にあると読み取ることができます。
日月神示には、こうしたカナ変換の「癖」があり、少し見方を変えただけで全く違う読み方になるため、神示解読には「完成形」が存在しないと言えます。
日月神示は「八通りの読み方がある」とされますが、解読に長い年月を掛けられた岡本天明氏や三典夫人が、たびたび解釈を更新なされたのは、こうした事情があるからだと思います。
神示は数字や記号などで基本的に書かれるため、あまり平仮名や漢字体で降ろされることはなかったと思われます。
そのため読み仮名をつける際には、「頭の体操」が必要なケースが多いのでしょう。
特に「荒れの巻」に関しては、ネタバレ的な内容が含まれるため、おそらく降ろされた天明氏らが意図的に「漢字変換」を行い、わざと直感的に解読困難な状態にしていたのではないかと思います。
同巻に「面白に秘解成答字理ぞ」とありますが、これを私が読んでみると「おもしろに紐解く、鳴門の道ぞ」という文章になります。
「二」は「に→の」に転換できるので、ここでは「つぐ」と読まずに「の」としました。
この解読は「パズル感覚」に近いものがあり、日月神様とのトンチの勝負です。
日月神示が予言的、暗喩的な表現をすることで「謎解き」の妙味が長年、ファンを惹きつける要因になっています。
「笑いのない教えにして下さるなよ(黄金の巻・第八十二帖)」とあるように、これらは日月神様のユーモアが日月神示解読の一部になっているのだと思います。
そもそも原典が「数字や記号」である日月神示は、どうしても文脈上の表記ブレや誤読を避けることができません。
仕組みとして「こうである」と断定できる要素は初めから存在しないため、日月神示は「八通り」どころか読む人によって全く捉え方が変わります。
日月神示は原典解釈が困難であるからこそ、権威や原理主義が発生する要因を持たず、その内容が人の「道」であるがゆえ、教えに「戒律」を持つことがありません。
「龍音の巻・第七帖」に「戒律ある宗教は亡びる」とありますが、主に経典とされるものは「誤読」を許すことがないため、講釈が一辺倒になりがちです。
そこに「宗教的権威」が生じると文脈に多様性が許されなくなり、解釈の枝分かれした学派を弾圧するなどの現象も起こりえます。
この「内輪揉め」とも言える解釈の奪い合いが、宗教の寿命を縮めることに繋がっているのかもしれません。
ゆえに「宗教的権威」の生じようのない「日月神示」は、誰もが自由に解釈できるからこそ永遠に「弥栄える」と言えるのです。
さて、今回は上記「荒れの巻」の読み方を刷新したことで、より見えてきた部分を広げていきたいと思います。
私は以前から、「真の天照大御神は伊奘冉命である」と述べて来ましたが、その論拠を明確に示したことはありませんでした。
「高皇産日神は伊奘冉神である」など、一般的な神道解釈から外れた見解ばかり述べてきましたが、「日月神示は実際の神界の真相を語っている」という前提として考えれば、その文脈の方が自然なのです。
それを頭に入れた上で、一つの読み方として聞いて頂きたいと思います。
天照大御神が女神の理由
実は地球上の神話で、「太陽神」が男神である説話の方が多いそうです。
エジプト神話の「ラー」や「アメン」、ローマ神話の「アポロン」と「ヘリオス」、メソポタミアに信仰された「シャマシュ」、インド神話では「スーリヤ」、それを受けての仏教「大日如来」、インカ文明では「インティ」、アステカでは「ウィツィロポチトリ」と、それぞれが「男神」とされます。
太陽神を女神とするのは、北欧神話では「スール」の他に特筆してあまりなく、日本のアイヌでは「トカプチュプカムイ」を天照大御神と同様、女神とします。
ここに日本神話の連続性を感じますが、世界を見回して太陽神を女性格とする神話は、割合として少ないのが確認できます。
「太陽」は昼間や夏は強く照りつけ、天体としての力強さで言えば「男性格」になるのも直感的に理解できます。
対して「月」は満ち欠けがあり、時に姿を見せない日もあり、静かに闇の空を照す姿は確かに「女性的」です。
ゆえに、「日=陽=男性」と「月=陰=女性」という中国陰陽思想的な観念こそ、むしろ世界共通と言えるのです。
日本の「天照大御神」が女神であるとする理由には、飛鳥・奈良時代の「記紀」編纂時の政治的意図があったという説もありますが、「ホツマツタエ」など偽書とされる古史古伝には、天照大御神を男神とする説もあります。
ただ、日本語の成立に大きく関わった琉球の神話には、「アマミキヨ」と「シネリキヨ」と呼ばれる、「姉弟」の始祖神が存在します。
これは北海道、アイヌ民族の「トカプチュプカムイ」が太陽を司る女神であるとすれば、「アマミキヨ」も本土の天照大御神に通ずる女神である可能性が高いです。
これらの神話は東南アジア系の言語分布と繋がりが深いことから、インド以東に根づいた神話観と考えられます。
神話の文化的系統から鑑みて「日本語」の言語学的系統と「太陽神女神説」は、強い親和性があると考えられます。
実際の神界で「太陽を司る神格が女神であるか」は置いといて、日本では先んじて「太陽神は女神である」という価値観が伝承として広がっていた可能性があります。
ゆえに日本の国家神道が太陽神「天照大御神」を女神としてお祀りするのは、伝統的な面から考えても納得のいく説明はつきます。
しかし、日月神示に示された「伊奘冉命」が太陽神であり、「真の天照大御神」とするには些か飛躍があります。
そこで、「伊奘冉命」とされる御神格がどういう神様であるのか、改めて考えていきたいと思います。
実は日本神話の礎たる「日本書紀」にも「古事記」にも、伊奘冉命と「太陽神」を結びつける文言は殆ど存在しません。
「記紀」はどちらも、二柱が「天地開闢」の後に「三貴子」をお産みになられ、御子神に「太陽」と「月」と「滄海原」をそれぞれお任せになられています。
つまりは宇宙創造の後、地球より先に太陽と月があるはずですが、神々の司宰は「国産み・神産み」の後になっているのです。
だから「記紀」をベースにした日本神話で考えると、伊奘冉命が「太陽神」であるという発想には到底至ることができません。
そのため「真の天照大御神は伊奘冉命である」と読み解ける文献は、日月神示以外にはなく、それも難解な「荒れの巻」を読んでようやくわかる程度のことです。
では「日月神示」で伊奘冉命が「天照大御神」とされる論拠は、どこまであるでしょうか。
「伊弉諾命」は男神とされるため、神示では「月と地を司る」とされ「月読命」と「素戔嗚命」に比定されている上では、神の性別に対する違和感はありません。
伊弉諾命が天照大御神と「誓約」を行った素戔嗚命とするなら、対する天照大御神を「伊奘冉命」と比定するのは順当かもしれません。
ただ、それだけでは論拠に乏しいので、逆に天照大御神こと「日の神」が、なぜ世界の神話にあるように男神ではなく女神であるのか、その部分を考えてみたいと思います。
「黄金の巻・三十五帖」には、こうあります。
「お父様が![]() ひの大
ひの大![]() 三〇おおかみさま、お母様が
三〇おおかみさま、お母様が![]() つきの大
つきの大![]() 三〇おおかみさまなり」
三〇おおかみさまなり」
「お母様」のところでは「![]() つき」とされることから、この文面だけを読むと「月の神」が母神、つまり月の司宰神であられる伊弉諾命が「男神」とされるには矛盾が生じてきます。
つき」とされることから、この文面だけを読むと「月の神」が母神、つまり月の司宰神であられる伊弉諾命が「男神」とされるには矛盾が生じてきます。
ここで「記紀」の伝承に戻りますが、伊弉諾命と伊奘冉命が結婚をする際、「天の御柱」に向かい合い、伊奘冉命は「左回り」に伊弉諾命は「右回り」にそれぞれ回り、出会ったところでプロポーズしますが、伊奘冉命が最初に声を掛けたことで「ヒルコ神」を産んでしまいます。
この場合、主題としては「女性がリードした」ことが問題とされますが、「日本書紀」の原文を読んでみると最初「伊弉諾命が左回り、伊奘冉命が右回り」であり、その「回り方」を改めたように読めます。
つまり、記紀共に男神は「右回り」でなければならず、女神が「左回り」でなければ順序を違えてしまうのです。
「黄金の巻・第五帖」には、こうあります。
「ものうむ始め、女、目的たてるとスコタン、種から生えたものは渋柿じゃ、接ぎ木せねば甘柿とはならん」
これは「産む」時に、伊奘冉命が先にプロポーズをしたことの失敗を彷彿とさせます。
この「産む」は女神である伊奘冉命を連想させ、「素戔嗚命」を彷彿とさせる「成る」という言葉が、伊弉諾命への繋がりを見せる一文があります。
「ナルとは成る言(こと)ぞ、成るは表、主ぞ、ウムとは「(六芒星の中に丶)」のこと、生むは裏、従ぞ、ナルは内、ウムはソト、ナルには内の陰陽合わせ、ウムにはソトの陰陽合わせよ(同・第四十七帖)」
ここで「産む」という概念には「渦巻」という「水の属性」があることがわかります。
とすれば、順当に考えて「産む」を司る伊奘冉命は、むしろ「月=水」の属性を持つがゆえに伊弉諾命と「逆の役割」になっていると言えるのです。
しかし、日月神示全文通して、「伊弉諾命は月地を司り、伊奘冉命は天と日を司り、二柱が合わさりミロクの世を司る」というテーマは一貫しています。
ここで参考になるのが、「日の出の巻・第二十二帖」の一文です。
「左は火ぞ、右は水だぞ、火の神と水の神ぞ、日の神と月の神だぞ」
つまり、「左=火=日」であり「右=水=月」を司る神となります。
また「天つ巻・第三十帖」には、こうあります。
「手足は沢山は要らぬのだぞ、火垂(ひだり)の臣と水極(みぎり)の臣とあれば良いのだぞ、「ヤ」と「ワ」と申してあろうがな」
神示でよく出てくる「ア・ヤ・ワ」を「御三体の神様」に当てはめてみると、「天の御三体」は「ア=天御中主」「ヤ=高神産日神」「ワ=神産日神」となり、「地の御三体」に当てはまると「ア=つきさかきむかつ姫(現天照大御神)」「ヤ=伊奘冉命」「ワ=伊弉諾命」となるはずです。
ゆえに伊弉諾命が「左回り」ではいけなかったのは、男神であられる伊弉諾命が「水極の臣」であったからではないでしょうか。
ならば「火垂の臣」である伊奘冉命が「左回り」だと正解で、「右=水極(みぎ)」であってはならない理由と考えられます。
そして「左が火属性、右が水属性」という図式は、女神の天照大御神は伊弉諾命の「左目」からお産まれになり、男神の月読命は「右目」、素戔嗚命は「鼻」からお産まれになられている説話にも繋がってくるのです。
奇しくも、神界を司る二柱のご活躍を伺える文章が、「黄金の巻・第二十三帖」にあります。
「神様も神様を拝み、神の道を聞くのであるぞ、それはひ(◯に丶)とひだり(左向きの渦巻)とみぎり(右向きの渦巻)とによって、自分のものとなるのじゃ、融けるのじゃぞ」
天界を司るのが「左回りの渦」であられる伊奘冉命、「右回りの渦」であられる伊弉諾命の二柱によって「日・火」と「月・水」、そして地球にまつわる全ての神々が統治されているのだとしたら、「神の道」が「天日月大神」に繋がっている理由にもなります。
これらを論拠として「伊奘冉命が女神でありながら太陽神である」説明はつきます。
また蛇足かもしれませんが、「星座の巻・第四帖」には以下の記載があります。
「身体中、黄金に光っているのが、国常立大神のある活動の時の御姿ぞ、白金は豊雲野大神であるぞ」
この「黄金に光るお姿」は太陽のように感じられますが、「ある活動の時」というのが曲者で、月は満ち欠けがあり、黄金に輝く完全なる姿の時は「満月」の日にしかありません。
天体の色は季節や時間によって違うのですが、常に「白く輝いている」のが「太陽」で、たまに赤くはなりますが太陽が黄色く見えたら「病気」と言われます。
「国常立大神」は素戔嗚大神、すなわち伊弉諾命と神示では同定可能なので、やはりここでも伊奘冉命が「豊雲野大神」であり、太陽神である確証が得られます。
しかし、「日=火=父」が男性格であるのは変わりなく、それでも女神が太陽神とされる不一致感は拭えません。
次の章では、そもそも「神様」と御役目の関係について、掘り下げて説明していきたいと思います。
神も「身体」と「魂」をもつ
「日の出の巻・第五帖」には、興味深い一節があります。
「右に行こうとする者と左に行こうとする者と結ぶのが「結び」の神様ぞ、結びの神様とは素盞鳴の大神様だぞ、この御用によって生命現われるのぞ、力生れるのぞ、「結び」がまつりであるぞ、神国の祀りであるぞ、神はその全き姿ぞ、神の姿ぞ、男の魂は女、女の魂は男と知らせてあろうがな」
ここで「素戔嗚大神」とは「伊弉諾命」に比定しうる神格ではなく、「伊弉諾命・伊奘冉命」二柱の神能を神格化した神と考えられます。
「大神」とは「神を束ねる御神格」を意味するので、厳密に「素戔嗚神」が伊弉諾命でも間違いはないでしょう。
この一文で気になるのは、「男の魂は女、女の魂は男」の部分です。
先の「黄金の巻・第四十七帖」に「ウムとは「(六芒星の中に丶)」のこと、生むは裏、従ぞ」とあるように、女神であり「水属性」の御身体を持たれる伊奘冉命が「産む」のは理解できます。
先に挙げた「日の出の巻・第二十二帖」には、またこのような文章があります。
「水は身を護る神だぞ、火は魂を護る神だぞ、火と水とで組み組みて人ぞ、魂と水を組んで人ぞ、身は水で出来ているぞ、火の魂入れてあるのだぞ、国土も同様ぞ」
つまり、「魂と身」で構成される人間の「身」は「水属性」であり、「魂=日」は「火属性」となります。
伊奘冉命が水属性の御身体を持たれていたからこそ、「火」の司宰神であられる火迦具土命をお産みになられた後、身体を壊されて鬼籍に入られたということではないでしょうか。
「身」は神示的表現であれば「◯」で、「魂」は「・」です。
「火と水」組み合わせて「◉(神・キミ)」とされるので、性別は別として神の御身体にも「神霊(体)=◯」「神魂=・」が存在することになります。
伊奘冉命の神魂が「日=火」だとしたら、御霊体が「女性」であり、水属性の御身体を持っていてもおかしくありません。
同様に、伊弉諾命の神魂が「月=水」とすれば、男性の御霊体であっても水属性を司ることに矛盾は生じません。
ここで「日の出の巻・第五帖」の「男の魂は女、女の魂は男」という文言が生きてきます。
伊弉諾命の神魂は水属性であるから「女性格」であり、伊奘冉命の神魂は火属性のため「男性格」なのです。
ゆえに、女神であられる伊奘冉命が「天照大御神」として太陽(日=火)を司っているのも、無理のない説明になります。
そして神の霊体に内包される「神魂」は、二柱の産みの神である「ナギの神・ナミの神」に繋がるとすれば、「天の御三体の神々」であられる「高神産日神・神産日神」を「御祖」に持つと考えられます。
「記紀」では、別天津神五柱は「純男」とされ、性別を持たないか単身の男神とされますが、これらの「神々の皇御祖」が男性格とすれば、日を司る「ナミの神」が男神の御魂を持っていてもおかしくありません。
「記紀」伝承によると宇宙創生以降、初めて「人」の形を持った神が生まれたのは、「国常立尊」からであるとされます。
「国常立尊」と「豊雲野尊」は二柱の別の御働きによる御神格なので、やはり神が性別を持ったのはこの代からと考えて良いのではないでしょうか。
ゆえに初めて「男女」の交わりをしたのが「伊弉諾命」と「伊奘冉命」という神話は、記紀と日月神示に共通した見解となり、記述に若干ブレのあった部分が統合されるのです。
二柱が「日=火」と「月=水」という対極のエレメントを司り、また「男女」と「姉弟」という真逆の関係でありながら、「夫婦」として互いに求め合うからこそ、例え神であろうと仲違いもあろうことは頷けるのです。
この「正反対の性質を求める」という宇宙的な性格は、岡本天明氏の筆と思われる「地震の巻」に詳細が書かれていますが、「富士の仕組み」「鳴門の仕組み」に関わる重大な要素となるので、改めて記事にしたいと思います。
全ての神々は二柱に繋がる
まとめとして、冒頭に紹介した「荒れの巻」の解説に戻ります。
「字」を「つき・つぎ」と読むことで解像度が高い解読が可能になったという話をしましたが、「伊奘冉命」の「日神」という神格はそのままに、伊弉諾命が「天照大御神」としての「高天原の最高神」という御位を継承することは、以下の一文に見られます。
「月日つきひ出で開きに、秘文ひふみ開き、字つきの玉ひ開く極み、那美なみ秘継ひつぐ道ぞ」
これをわかりやすく口語訳に変換すると、こうなります。
「月日出で開き、一二三開き、月の日開く極み、那美の日嗣ぐ道ぞ」
「黄金の巻・第四十九帖」には「月日様では世は正されん、日月様であるぞ、日月様が「記号(ひつきおおかみ)」様となりなされて、今度のイワト開きあけるぞ」とあります。
これまでは「真の天照大御神」こと伊奘冉命が岩戸の中におられたため、地上における「日月」を司る神は伊弉諾命と、その御子神であられる「つきさかきむかつ姫の神」が「天照皇大神宮の神」として伊奘冉命の代役をなされていた、ということではないでしょうか。
ゆえに「父と娘」でなされていた「月日様」では「闇の世」のままで、世を正すのは伊奘冉命と力を合わせた伊弉諾命の二柱が「日月大神」として君臨する世ということだと思います。
「青葉の巻・第十七帖」には「日の神ばかりでは世は持ちては行かれんなり、月の神ばかりでもならず、そこで月の神、日の神が御一体となりなされて、ミロク様となりなされるなり」とあり、「ミロクの世」はやはり伊弉諾命と伊奘冉命の二柱による統治を意味しています。
これまで、「地の御三体の神々」として伊弉諾命を補佐していたと思われる「つきさかきむかつ姫」とは、「撞賢木厳御魂天疎向津姫命」すなわち「現・天照大御神」に比定可能です。
つきさかきむかつ姫が、母神の代役をしながら父神の補佐が可能なのは、かの女神が二柱の神能をちょうど半分ずつ受け継いでいるからではないでしょうか。
「撞賢木厳御魂天疎向津姫命=瀬織津姫命」について書き始めると、またとてつもない文章量になってしまうので控えますが、おそらく二柱の神能を受け継ぎ「素戔嗚神」として御働きなさる神様は、一柱くらいとは考えるべきではないと思います。
二柱の「神産み・国産み」では地球上に遍く八百万の神々をお産みになられておられるので、あらゆる神の御働きは二柱に繋がる性質を有しているのではないでしょうか。
その二柱も、元を辿れば「天の御三体の神」であられる「天御中主神」「高神産日神・神産日神」に行き着きます。
すなわち、この全宇宙の神々のルーツは皇大神に繋がり、その神々を統べるのが「天日月大神」であられると考えうるのです。
かの「大日月(地)大神」と「天日月大神」は厳密には同じではなく、「大日月大神」は全宇宙の神々を「類魂」として束ねる御神格であり、つまりは神々の「総体」です。
「天日月大神」とは神々の総体を取りまとめる権威の御神格であり、それは伊弉諾命と伊奘冉命に委ねられていることになります。
私たちが地元の神社とか、推しの神様とのご縁を感じる際には、氏神や産土神など親しみ深い神様を通じて、「大日月大神」や「天日月大神」に辿り着くことが可能です。
おそらく、「1945年の旧9月8日」から天界の「岩戸開き」がなされたことで、地上の時系列として「天日月大神」をお祀りすることが可能になっていると思います。
しかし、それから80年後の今なお「地の岩戸開き」は行われていないため、2025年現在も「闇の世」であり真の天照大御神の御威光は届かず、天日月大神の御神威が示されないのです。
その「地の岩戸開き」を行うのは私たち人間が「地の日月神」であるという自覚を持ち、真の「神道」に立ち返ることにあります。
そのヒントもまた「日月神示」にあります。
「日月神示とは何か」と問うならば、私は「実践のための手引き書」だと思いますし、その知識は「宇宙哲学」に近い「認識論」に関する文書だと思っています。